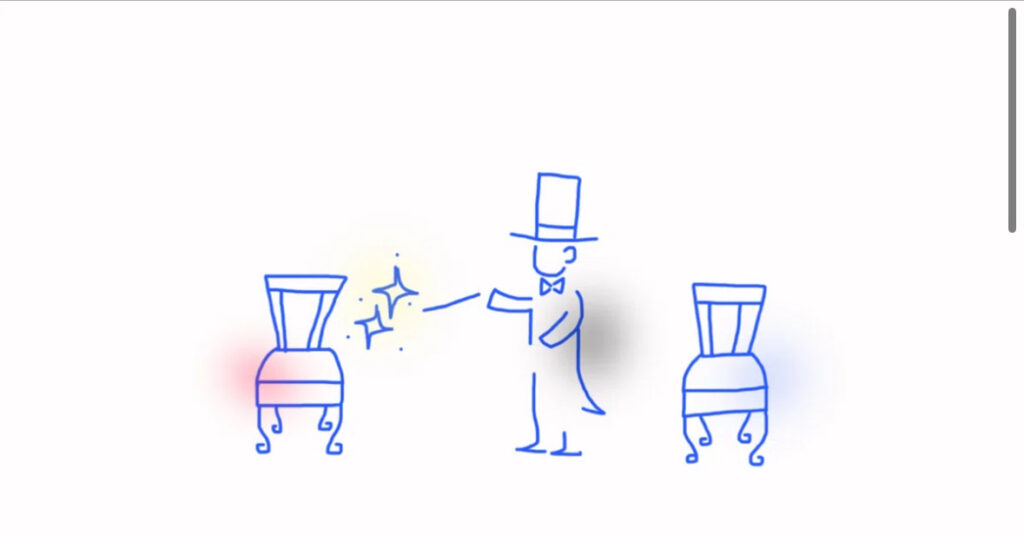幸せの配達人

ハルオは、自分を「ついてない男」だと思っていた。
転職に失敗してアルバイトを掛け持ちする日々。給料は少なく、服も古びたものばかり。人付き合いもうまくなく、いつも一人でコンビニ弁当を食べる生活。
「俺がいるだけで空気が悪くなる気がするよ」
彼は自分の存在価値を見出せず、ただ日々をやり過ごしていた。
ある日、ハルオは荷物の配達のアルバイトを始めた。小さな運送会社の軽トラックに乗り、指定された住所に荷物を届ける仕事だ。「人と話す時間は短いし、ミスさえしなければ目立たないで済む」と考えて選んだ仕事だった。
ところが、この仕事を始めてから奇妙なことが起こり始めた。
最初の出来事は、町外れの小さな花屋だった。ハルオが届けたのは、珍しい蘭の花。それを受け取った老夫婦は満面の笑みを浮かべた。
「ありがとう!これで、息子夫婦の結婚記念日に間に合うわ!」
「いや、俺は運んだだけで……」と戸惑うハルオをよそに、老夫婦はお互いに喜びを語り合い、その場の空気がぱっと明るくなった。
次に訪れたのは、学生寮だった。中から出てきた若い女性は、顔をこわばらせながら「待ちに待った教科書が届きましたか?」と尋ねた。
「ええっと、これかな……?」
女性が封筒を開けると、瞬く間にその顔が輝いた。「これで明日の試験に間に合う!ありがとう!」
それからというもの、ハルオが配達に行く先々で、受け取る人たちは皆、どこかしら幸せそうな表情を浮かべた。
やがて、ハルオは自分の仕事にある種の誇りを感じるようになった。
「俺はただ荷物を届けてるだけなのに、みんなが喜んでくれる。これって、ちょっといい仕事かもな」
そんなある日、ハルオは会社から「特別な荷物」を預けられた。それは、近所の古びたアパートに住む独居老人への配達だった。
アパートに着くと、中から聞こえてきたのは小さな独り言だった。
「もう誰も訪ねてこないな……私も、このまま消えるのかな」
ハルオは荷物を届けると、思わず言った。「あの……俺がこの荷物を届けられてよかったです」
老人は驚いた顔をして、「君が?」と問い返した。
ハルオは肩をすくめて答えた。「俺、いつも何も特別なことなんてしてないんです。ただ運んでるだけなんですけど、なんだかみんな喜んでくれるんです」
すると老人は、しみじみと言った。「それが一番素晴らしいんだよ。君は、みんなを幸せにする存在なんだな」
その言葉が、ハルオの胸に深く染み入った。
その夜、ハルオはふと自分の仕事を振り返った。荷物を運ぶという一見地味な仕事。それでも、自分の手で誰かを笑顔にできていた。それが少しだけ誇らしかった。
次の日、彼は同僚の間でも明るい表情を見せ始めた。「何かいいことあったのか?」と聞かれるたび、ハルオは「いや、なんでもないけどさ」と笑った。
ハルオ自身も気づかないうちに、彼の笑顔が周りの人々を明るくしていた。
そして、彼は知らなかった――町のあちこちで、彼のことを「しあわせの配達人」と呼ぶ声が増えていることを。
ハルオは、自分が誰かを幸せにしているという実感を持ち始めていたが、それがどうしてなのかは全く分かっていなかった。ただの偶然だろう――彼はそう思い込むようにしていた。
しかし、ある日、会社に奇妙な手紙が届いた。それは、ハルオ宛の手紙だった。
「ハルオ様へ」
普段、客先から手紙が来ることなどない。それだけで十分に不思議だったが、さらに不可解なのはその内容だった。
「あなたは特別な力を持っています。それは、あなた自身が意識していないものです。ただ運ぶだけで人々を幸せにできるのは、あなたが“しあわせの種”を届けているからなのです。
この力は、あなたの祖先から受け継がれたものです。そして、それをどう使うかはあなた次第です。
手紙には差出人の名前も連絡先もなかった。ただ、最後にこう書かれていた。
「運び続けなさい。それが、あなたの使命です。」
手紙を読んだハルオは頭を抱えた。「しあわせの種?祖先からの力?」そんなものが自分にあるなんて信じられなかった。だが、心のどこかで思い当たる節があった。
「そういえば、昔から何となく、俺が誰かに何かを渡すと喜ばれることが多かった気がするな……」
幼い頃、友達に貸した鉛筆一本でその友達が「テストで100点を取れた!」と喜んでいたことを思い出した。何気なくあげた飴玉が、落ち込んでいたクラスメイトを元気づけたこともあった。
「あれが……俺の力だったのか?」
半信半疑のまま、ハルオは配達を続けた。しかしその日、いつもとは違う出来事が起きた。
ハルオが荷物を届けたのは、町で有名な雑貨店だった。そこにいたのは、最近元気のない様子で噂されていた店主の女性だった。
彼女が受け取った荷物は、海外の工芸品だったらしい。最初は普通に受け取っていたが、ふとその箱を開けると目を見開いた。
「このデザイン……私がずっと探していたもの!」
それは、彼女の亡き夫が生前大切にしていたデザインにそっくりのものだったのだ。ハルオが届けたその品物を見て、彼女は涙ぐみながら微笑んだ。そしてこう言った。
「あなたが運んでくれるものには、いつも不思議な幸せが詰まっている気がするのよね。まるで天使みたい」
その言葉にハルオは立ち尽くした。
家に帰ったハルオは、もう一度あの手紙を見返した。そして、思わずつぶやいた。
「俺の力って、本当にあるのかもな……」
その夜、彼は夢を見た。そこには穏やかな顔をした年老いた男性が現れた。
「ハルオ、お前は私たちの血を引く特別な存在だよ。お前が運ぶものには“幸せの種”が宿る。だが、その種を本当に育てるのは、お前が相手に込める優しい気持ちだ。だから、自信を持ちなさい」
目を覚ましたハルオは、これがただの夢ではない気がしていた。
翌朝、ハルオは軽トラックに乗り込むと、空を見上げて思った。
「誰かの幸せを運べるなら、それが俺の使命なんだな」
その日、彼が配達した荷物にはまたも笑顔が広がった。彼が運ぶ“幸せの種”は、相手の心に届き、そこで花を咲かせていった。
そして、そんな日々を重ねるうちに、ハルオ自身も幸せを感じられるようになっていた。
彼はまだ知らない。この先、自分がどれほど多くの人々の人生を変えることになるのかを