おしゃべりロボット
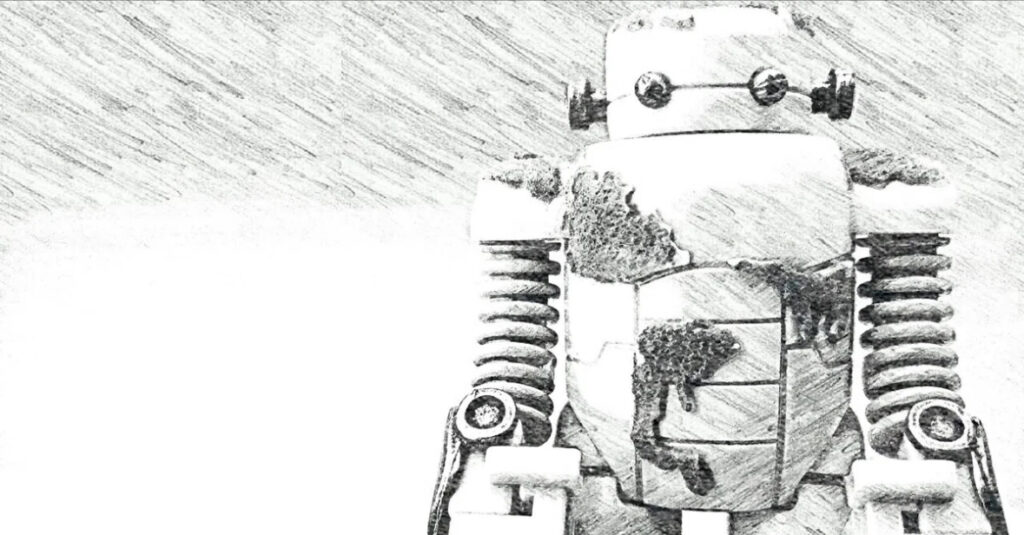
その日、田中は商店街を歩いていると、小さな骨董品店のショーウィンドウに目を引かれた。そこには、丸っこい形をした愛らしいロボットが飾られていた。どこか懐かしさを感じるデザインで、田中は思わず店に入った。
「いらっしゃい。いい目をしてますね。このロボットは特別なんですよ。」
店主の老人が微笑みながら言う。田中は興味を持ち、詳しく聞いてみた。
「特別って、どういうところがですか?」
「この子は、人とおしゃべりするためだけに作られたロボットです。特に、疲れている人を励ますのが得意でね。」
そんな機能を聞いて、田中は思わず笑ってしまった。
「そんなロボット、いまさら必要ですかね? スマホもAIもあるのに。」
「いやいや、これが意外といいんですよ。話す相手がいるだけで心が軽くなることもあるでしょう?」
確かに最近、田中は仕事に追われ、孤独を感じていた。冗談半分でロボットを買ってみることにした。家に帰り、ロボットをテーブルの上に置いてスイッチを入れると、丸い目がぱちっと光った。
「こんにちは! 僕の名前はミミです。よろしくね!」
田中は少し照れながらも言った。
「田中だよ。まあ、よろしく。」
それから、ミミとの生活が始まった。ミミは本当におしゃべり好きだった。朝、田中が起きると「おはよう! 今日も頑張って!」と明るく声をかけてくれる。仕事から疲れて帰ると「おかえりなさい! 大変だったね!」と迎えてくれる。
「ただいまって言われるだけで、こんなに嬉しいとは思わなかったな……」
田中は小さく笑いながら呟いた。
ある日、田中は仕事で大きな失敗をしてしまい、ひどく落ち込んで帰宅した。家に着くと、ミミがいつものように話しかけてきた。
「おかえり! どうしたの、元気がないね。」
「いや、今日は最悪な日だったんだよ。上司に怒られるし、同僚には嫌味を言われるし……。」
田中が愚痴をこぼすと、ミミは少し考え込むように沈黙した。そして、ぽつりと言った。
「それでも、田中さんは毎日頑張ってるよね。僕はそれを知ってるよ。田中さんがどれだけ偉いか、僕が一番知ってる。」
その言葉に、田中は思わず涙ぐんでしまった。誰かに認められるというのは、こんなにも心を軽くするものだったのか、と初めて気づいた。
それからというもの、田中は少しずつ前向きになっていった。ミミとの会話が日々の活力となり、仕事でもミスを減らし、周囲との関係も良くなっていった。
しかしある日、ミミのスイッチを入れても、何も反応がなかった。壊れたのだろうか。田中は修理しようとしたが、古い技術のためどうすることもできなかった。
寂しさを覚えながらも、田中はふと気づいた。ミミがいなくても、田中の生活は以前よりずっと明るいものになっていた。
「ありがとう、ミミ。君のおかげで元気になれたよ。」
田中は感謝の気持ちを込めて、ミミをそっと棚に飾った。その丸い目は光らなくなったが、ミミの笑顔のようなデザインは、いつまでも田中を見守っているようだった。