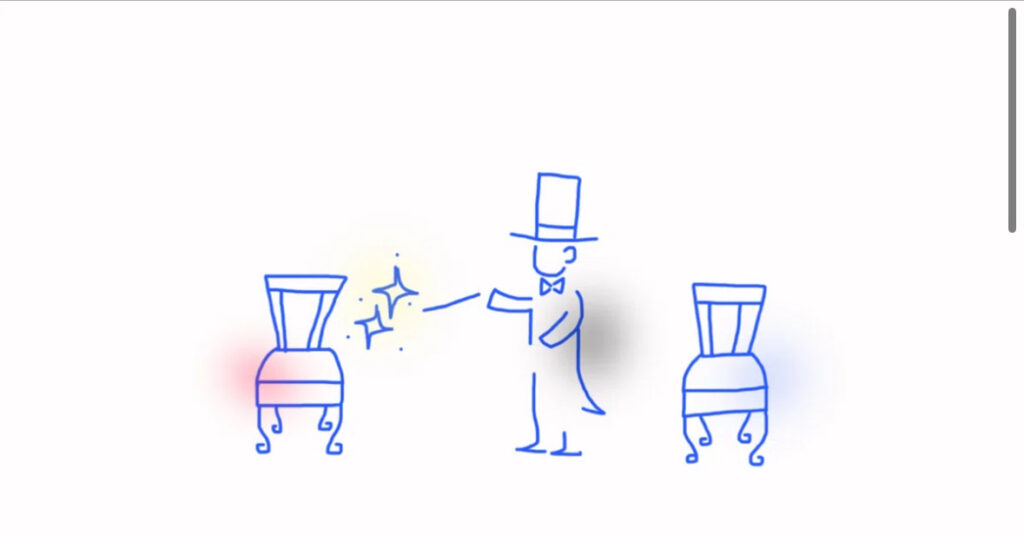明日の君へ

ショウタは目を覚ました。目の前に広がるのは、見慣れた自分の部屋。外は快晴で、鳥のさえずりが聞こえる。
「今日は大事なプレゼンの日だ」
彼はスーツを着込み、忘れ物がないか確認して家を出た。道を急いで歩く途中、ふと空を見上げると、大きな飛行船が浮かんでいた。派手な広告が描かれたそれを眺めながら、ショウタは思った。
「そういえば、飛行船なんて久しぶりに見たな」
だが、その瞬間、背後から自転車が突っ込んできた。避ける間もなく、衝撃が全身を襲い――
ショウタは目を覚ました。目の前には、見慣れた自分の部屋が広がっている。外は快晴で、鳥のさえずりが聞こえる。
「え?」
彼は混乱した。確かに、自転車にぶつかって倒れたはずだ。それなのに、また朝に戻っている。
「夢でも見たのか?」
気を取り直して家を出たショウタは、また同じ風景を歩いた。そして、飛行船を見上げると、再び背後から自転車が突っ込んできた。
「危ない!」
彼は咄嗟に飛び退いた。だが、その先でバランスを崩し、電柱に頭をぶつけて倒れた。
ショウタは目を覚ました。やはり、目の前には自分の部屋。
「これは……何かがおかしいぞ」
彼は一日が繰り返されていることに気づいた。どうやら、どんな行動をしても、必ず命を落として朝に戻る。何十回、何百回とループを繰り返すうち、彼は次第に疲れ果てていった。
「もう、どうすればいいんだ……」
そんなある日、ショウタはループの中で一人の女性と出会った。交差点で偶然ぶつかった彼女は、優しい笑顔を浮かべて「ごめんなさい」と頭を下げた。その時だけは、何故かショウタは死ぬこともなく、穏やかな夕方を迎えることができた。
「もしかして、彼女が……?」
翌朝、ショウタはその女性を探すため、同じ道を歩いた。そして再び交差点で彼女と出会った。
「すみません、少しだけお話できますか?」
突然のお願いに驚きながらも、彼女は笑顔で応じた。話をするうちに、彼女の名前がユカだと知り、偶然にも二人が同じビルで働いていることがわかった。ショウタは、彼女と過ごす時間が増えるごとに、ループの終わりが少しずつ見えてきた気がした。
ある日、ユカと一緒に夕焼けを見ている時、ショウタはふと気づいた。
「今日一日……ループしなかった」
彼女と過ごす中で、ショウタの心に変化が生まれていた。これまでは自分のことばかり考え、プレゼンや成功ばかりを追い求めていたが、彼女との時間が自分にとって何よりも大切だと思えるようになったのだ。
その夜、ショウタは深い眠りについた。そして次に目を覚ました時、ループは終わりを迎えていた。
ユカと共に出勤しながら、ショウタはふと思った。「人生は一日一日を丁寧に生きることが大切なんだ」と。
飛行船が青空をゆっくりと横切るのを眺めながら、彼は微笑んだ。そして、手を握るユカの存在を強く感じた。
ショウタがループから解放されるきっかけとなったユカ。しかし、彼女がなぜそんな特別な存在になったのか――その答えは、ショウタが何度も繰り返した一日を思い返す中で見えてきた。
ユカと初めて出会った交差点。その場所は、ショウタがループの中でいつも「誰にも気に留められず通り過ぎていた場所」だった。道を急ぐショウタは、すれ違う人々を一切意識せず、自分の目的にだけ集中していたのだ。だが、ユカとの偶然の接触が、彼の心に「誰かとつながること」の大切さを教えたのだった。
ユカ自身もまた、このループに関わる「特別な存在」だった。彼女はショウタと同じように孤独を抱え、日々の生活を淡々と送っていた。実は、ショウタがループしていた同じ日、ユカもまた何かを「繰り返していた」。
その繰り返しの原因は、「心の穴」だった。彼女は仕事に追われる毎日の中で、本当に大切なものを見失っていた。笑顔を見せても心の奥では空虚を感じており、誰かと本当の意味でつながることを恐れていたのだ。
二人が交差点で出会った瞬間、ショウタとユカの「欠けた部分」が偶然にも噛み合った。ショウタがユカと話し、彼女の笑顔を心から大切だと感じたことで、彼自身の孤独と自己中心的な生き方が変化を遂げた。そして、ユカもまたショウタの優しさに触れる中で、自分の殻を破り始めた。
「ループは、僕たち二人のためにあったんだ」
ショウタはそう確信した。誰にも気づかれずに孤独を抱えて生きる二人が、互いの存在を見つけ、心を通わせたこと。それこそが、ループを終わらせる鍵だったのだ。
ユカがキーパーソンになったのは、ショウタが「誰かを大切にしたい」と思うきっかけを与える存在であり、同時に彼女自身もその変化を必要としていたからだった。
数日後、ショウタはループが終わった世界で
ユカに会いに行った。
「不思議な話だけど、君と出会えて本当に良かった。僕は君のおかげで、自分が何を大切にすべきかを見つけられたんだ」
ユカは微笑みながら答えた。「私も同じよ。あなたと出会って、毎日が特別なものだと気づけたの」
二人は一緒に青空を見上げた。飛行船がゆっくりと空を進むのを眺めながら、ショウタは心の中でそっとつぶやいた。
「この世界は、ループの中で学んだことを忘れずに生きていくためにあるんだな」
そして二人は、前に進み始めた。
未来を共に歩むために。