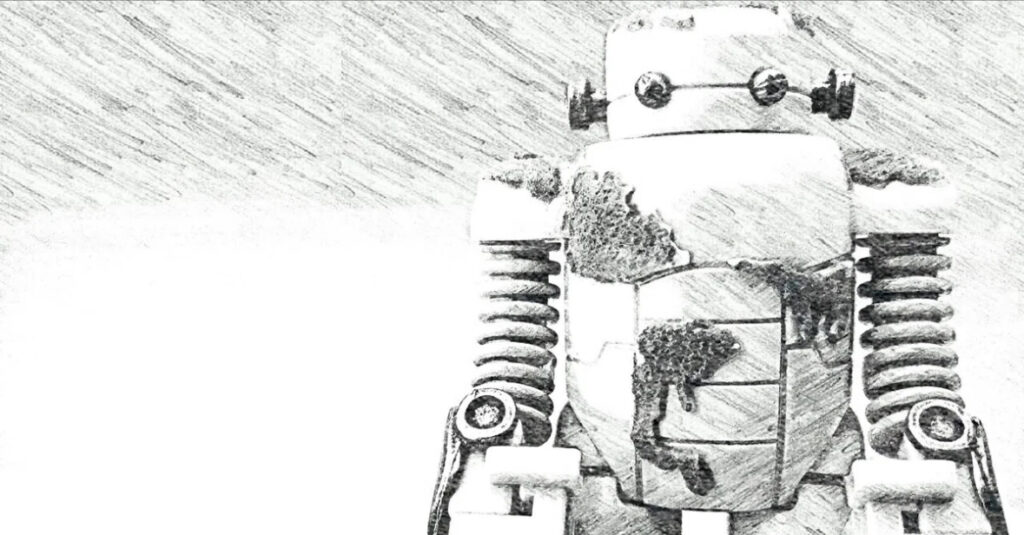最後のサービス

田中は、定年退職を迎え、悠々自適の生活を送っていた。ある日、突然の心臓発作で倒れ、気がつくと見知らぬ白い部屋にいた。
「ここはどこだ?」
周囲を見回すと、一人の案内人が現れた。
「田中様、ようこそお越しくださいました。ここは『アフターライフ・サービスセンター』でございます。」
「アフターライフ?つまり、私は死んだのか?」
「はい、そうです。しかしご安心ください。我々はお客様の生前のご希望に沿った死後の世界をご提供しております。」
田中は生前、特に宗教的な信念もなく、死後の世界について深く考えたこともなかった。
「私は特に希望など出していないが…」
「その場合、我々がいくつかのオプションをご提案させていただきます。」
案内人は微笑みながら、タブレット端末を操作し、いくつかの映像を田中氏に見せた。
- 天国プラン:美しい景色と永遠の安らぎが約束された世界。
- 輪廻転生プラン:新たな人生を別の形で再スタート。
- 幽霊プラン:現世に留まり、見守る存在となる。
田中は少し考えた後、質問した。
「これらのプランには費用がかかるのか?」
「いいえ、すべて無料でご提供しております。ただし、一度選択されますと変更はできません。」
田中は再び考えた。永遠の安らぎも、新たな人生も魅力的だが、現世に未練がないわけではない。
「幽霊プランを選んだ場合、家族や友人に会えるのか?」
「はい、ただし姿は見えず、声も届きません。ただ、そばで見守ることは可能です。」
田中は深く息をつき、決断した。
「では、幽霊プランでお願いしよう。」
「かしこまりました。それでは、こちらの契約書にサインをお願いいたします。」
田中がサインを終えると、突然視界が暗くなり、次の瞬間、自宅のリビングに立っていた。家族が悲しみに暮れている姿が見える。声をかけようとするが、やはり声は出ない。
しかし、家族のそばにいられることに安堵し、これで良かったのだと思った。
数日後、田中は家族が少しずつ日常を取り戻していく様子を見守っていた。自分の存在が家族の支えになっていると感じていた。
しかし、ある日、家族が引っ越しを決意した。新しい生活を始めるために。
田中は取り残された。新しい住人が引っ越してきても、彼らには何の感情も湧かない。孤独と虚無感が彼を包み込んだ。
「これが永遠に続くのか…」
田中は、自分の選択を後悔し始めた。しかし、もう遅かった。
田中が虚無感に苛まれていたある日、新たな異変が起きた。
リビングに設置されたテレビが突然光りだし、画面に見覚えのある案内人が映し出された。
「田中様、アフターライフ・サービスセンターです。いかがお過ごしですか?」
「いかがお過ごしも何も、完全に孤独だ!こんなはずじゃなかった!」
案内人は微笑みながら田中氏を見つめた。
「田中様、実はこのプランには試用期間がございまして、本日はその終了日となります。」
「試用期間?そんな話は聞いていないぞ!」
「契約書の小さな文字で記載がございます。ですがご安心ください。本日をもちまして再選択が可能となります。」
田中は少し期待に胸を膨らませた。
「つまり、別のプランに切り替えられるのか?」
「はい。ただし、これが最終選択となります。変更はこれが最後ですので、慎重にお選びください。」
案内人が再びタブレット端末を操作すると、画面には以前のプランに新しいオプションが加わっていた。
- 天国プラン:美しい景色と永遠の安らぎが約束された世界。
- 輪廻転生プラン:新たな人生を別の形で再スタート。
- 幽霊プラン:現世に留まり、見守る存在となる。
- 消滅プラン:存在そのものを完全に消し去り、無へと還る。
田中は最後の選択肢に目を見張った。
「…消滅プラン?」
案内人は淡々と説明を続けた。
「完全な無でございます。感情も意識も存在そのものが消滅し、真の安らぎを得られます。恐れることはございません。」
田中は考え込んだ。
「天国プランや輪廻転生は魅力的だが、本当に幸せになれる保証はない。幽霊プランはもう二度と選びたくない。そして消滅プラン…これが安らぎと言えるのだろうか?」
案内人は続ける。
「田中様、時間が限られております。決断をお願いいたします。」
田中は深呼吸をした。選択肢をじっくり見つめ、ようやく決意した。
田中はしばらく逡巡した後、意を決して言った。
「…消滅プランを選ぶ。」
案内人は静かに頷き、画面上に契約書を表示した。
「ありがとうございます。それではこちらに最終承認のサインをお願いいたします。」
田中が指を画面に滑らせてサインを終えると、部屋の光が徐々に薄れていった。やがて、周囲は完全な暗闇となった。
その暗闇の中で、田中の意識はまだ存在していた。
「これが消滅なのか?意識があるままではないのか…?」
しかし、次第に意識そのものが薄れていくのを感じた。感情が消え、記憶が霧散していく。名前、顔、そして家族の存在すら曖昧になっていく。
「これでいいのだ」と田中は思ったが、その思考すらすぐに消え去った。
完全な無――そこには時間も空間も存在しない。ただ無限に広がる静寂。田中は自分が消えたことすら認識できない世界へと溶け込んだ。
しかし、どれだけの時間が経ったのかもわからない無の中で、かすかな「気配」を感じた。それは田中自身のものではなかった。
突然、遠くから声が聞こえた。
「お疲れさまでした、田中様。消滅プランの体験はいかがでしたか?」
田中の意識が引き戻されるように、再び「存在」を感じた。目の前には例の案内人が立っていた。
「…どういうことだ?私は消滅したはずでは?」
案内人は微笑みながら答えた。
「実はこれも試験段階のプランでした。真の消滅を選ぶ前に、まず疑似的な消滅を体験していただく仕組みです。」
「つまり、私はまだ…存在しているというのか?」
「はい。そして、これで最終的な選択をしていただけます。真の消滅をご希望でしたら、今度こそ完全にお消えいただけます。」
田中は驚きと怒りで声を荒げた。
「ふざけるな!私はもう十分だ!何もかも終わらせてくれ!」
案内人は静かに頷いた。
「承知しました。それでは、今度こそ――」
田中の視界がまたしても暗くなった。その瞬間、彼の意識は永遠に消え去った。どんな気配も、痕跡も残ることなく、完全な無となった。
エピローグ
案内人はシステム画面を閉じると、次の名前を呼び出した。
「次の方、どうぞ。」
部屋のドアが開き、新たな一人が入ってきた。彼の顔には困惑が浮かんでいる。
「こちらは『アフターライフ・サービスセンター』です。どうぞお気軽にプランをご選択ください。」